

また、最近本当に長生きの犬たちが増えています。
9歳になる愛犬の年を私が初めて感じたのは、顔に白髪が出てきた辺りからです。
老犬になったらどのくらいのケアが必要なのか、老犬って一体何才からなのか、いろいろな不安がよぎるかと思います。
ドッグトレーナー目線から、そんな不安を少しでも解消できるお手伝いができたらなぁと思います。
老犬って何歳から?老犬の年齢の基準とは

ドッグフード業界や動物病院では7歳程度からシニア犬として扱われ始めます。
ただし、7歳くらいでは「老犬」という感じの老いは見られない犬の方が多いです。
白髪が顔に出てきたり、性格に落ち着きが現れたり、変化はもちろんあるのですが、動きの俊敏性はまだ見られます。
小型犬の寿命は大型犬と比べると長かったりと、犬種によって少し差は出てきますが、「老犬」らしくなるのはおよそ11~12歳頃からでしょう。
老犬の飼い方・接し方

老化で耳が遠くなる
「老犬」の老化現象として最も早く、かつほとんどの犬に多く現れるものは「耳が遠くなる」ということです。
体はピンピンしていていつも通りなのに、なぜか呼んでも来なくなったなど、思い当たることがあればただ聞こえていないだけかもしれません。
通常、それが回復したりそのための治療などは、犬の場合ありませんので、聞こえなくなってしまうことが必然です。
慌てずに、なるべく大きな声で呼んでみたり、身ぶり手振りを大きくしたり、耳のそばでてを叩いたりして、気づいてもらえるように工夫しましょう。
それらの合図が届かないほどの距離を離れて遊ばせるようなことは、安全上避けた方が良いでしょう。
老犬の白内障も注意したい老化の症状
次によくある老化現象として「白内障」があげられます。
素人目で見ても黒目が白くなっている犬は判断がつきます。全く見えなくなることもあるようで、壁にぶつかったりしてしまうこともあります。
それほどになってしまった場合は自ら歩き回ることを避けて寝ることが多くなります。
犬自身が不安になって鳴いたり、以前より呼ぶために鳴いたりすることが多くなる可能性がありますが、その都度、「トイレかな」「喉が乾いたかな」など、気にかけてあげましょう。
その他の犬の老化の症状・サイン


昼夜問わず睡眠時間が増える

犬は年齢を重ねるにつれ、睡眠時間が長くなると言われます。
ただし、犬種によっては元々良く寝る犬種もいます。
わが家のフレンチブルドッグも昼夜問わず睡眠時間が長い犬種です。
そういった犬種による違いはありますが、老犬になるにつれて成犬よりも睡眠時間が長くなる傾向があります。
食欲不振・食欲旺盛など食欲の変化
人間同様、犬も老犬になれば食欲に変化はあらわれます。
食が細くなって食べ残したり、今まで食べていたドッグフードに興味を持たなくなる食欲不振のケースだけでなく、
逆にやたら食事に執着して食欲旺盛になるケースもあるようです。
老犬の食事については、冨塚トレーナーの老犬の食事・ドッグフードについて記事でご確認ください
散歩を嫌がる様になる

元々散歩が嫌いな子もいますが、老犬になり老化の現れとして、散歩を嫌がる様になったり、元気に散歩ができる時間が短くなる傾向があります。
無理に急がせたりせず、愛犬の状態を観察しながら飼い主側の臨機応変な対応が大切になります。
老犬の散歩については、冨塚トレーナーの老犬の散歩はどうすれば良い?記事でご確認ください
階段の上り下りが辛そう
老犬になり足腰が弱くなると、階段の上り下りを嫌がる子が多くいます。
足の関節や腰の痛みなど原因はそれぞれ違いますが、老犬の足腰の衰えは下半身から来るケースが多いので、
いつもの散歩の時にしっかり様子を見ながら、変化を見逃さずにチェックしたですね。
口臭がきつくなる
犬の歯周病は成犬の時から気を付けなければいけない病気ですが、老犬になると歯周病にかかる確率が上がるとされており注意が必要です。
口臭は健康のバロメーターにもなるので、愛犬の口臭はチェックすべき重要ポイントです。
虫歯だけではなく、歯茎に炎症が起きていないかも確認してあげてください。
老犬になると下痢や便秘がちになる事がある
老犬になると、胃酸をはじめとした消化液の分泌が減ってしまい、消化器官が成犬の頃に比べて衰えてしまいます。
消化器官が活発に機能しない事で下痢や便秘がちになる子もいます。
消化に負担のかからないドッグフードに変えるなどの対策も検討する必要があります。
皮膚や被毛の変化
老犬になれば、皮膚や被毛にも当然変化が現れます。
毛が抜けたり、毛の色に変化が起きたり、成犬のころは見られなかった変化も起こります。
犬によっては、目ヤニが増えたり、耳垢が増えることも老化の変化として見られる事があります。

でも、いつも一緒にいる大切な愛犬の老化の変化にいち早く気づいてあげる事で、愛犬に負担の少ない生活を送らせてあげたいものですね。
老犬のトイレの介護について

介護といって思い浮かぶのが人間同様「トイレ」のことですね。
トイレを自力でできる(排泄する力があるという意)「老犬」であっても、足腰も弱りトイレまで歩いて行くのではなく、寝ていたところでそのまましてしまうことも多くなります。
そうなってもいいように、いつも寝ている場所には汚れても良い状態にしたり、おむつを活用したりして、元来きれい好きな犬が不快な思いをしないようにしてあげましょう。
あまりに体が汚れてしまったら、きちんと洗ってあげましょう。

室内ではなく庭で飼っていたのですが、凄く賢い犬でトイレも決まった場所にしかしない子でした。
老犬になり足が動かなくなってからも、前足だけで這うようにトイレを行っていました。
最終的にはそれもできなくなったのですが、犬は綺麗好きなのでトイレのお世話はきちんとしてあげないと、犬としてはとても不快な思いをしているのだと思います。
私達人間も老いればトイレの世話を誰かにしてもらう日が来てしまいますが、そのまま放置されたら凄く不快ですもんね。
犬だって同じなはずです。
トイレのお世話は大変ですが、犬は綺麗好きという事を忘れずに接して行きたいですね。
老犬の飼い方・介護で注意すべき事

犬の様子を観察し、変化を把握する
とにかく老犬になると今までできていたことができなくなったり、今まで積極的にしていたことをしなくなったりして、飼い主さん側が戸惑うことが多くなるでしょう。
認知症になってしまう犬も、以前よりペットが長生きするこの時代の結果として多くなって来ています。
何が前と同じようにできるのか、何ができなくなってしまったのか、犬の様子を見て日々把握していくことが大切です。
生活環境を考える

フローリングの場合、成犬でも犬が滑って関節を痛めたり、骨折をしてしまったりする事があります。
老犬になり関節にダメージを受けていたり、骨が弱くなってくると骨折や関節のトラブルのリスクは高まります。
タイルカーペットなどを敷き詰めて、愛犬が走っても滑らない様な対策もおすすめです。

タイルカーペットは汚れてもその部分だけ交換できますので便利です。
フレンチブルドッグは興奮しやすい犬種なので、フローリングを足を滑らせながらでも走り回ってしまいます。
犬用の滑らないワックスもある様ですが、タイルカーペットが手軽で確実に対策できるのでおすすめです。
老犬の食事・ドッグフード、食べない時の対策

若いときから食欲が旺盛だった犬は、老犬になっても毎食ご飯を待ち望んでくれます。
それに反して以前から偏食傾向があった犬は、老犬になってもそういう傾向は続きます。
老犬になって、より食欲が無くなってしまうと体力の低下に直結して行きますので、ドライフードを与えていた犬には、臭いが強く食べやすいウェットフードなどを多めに混ぜたりしても良いでしょう。
基本的にはシニア用のドッグフードに徐々に切り替えて、運動量太らないようにそれぞれの犬に合わせて与える量を調節していきましょう。
いずれにせよ、何日も食べないようなことがあってはいけませんので、その際はすぐに獣医さんに相談してみましょう。
毎日食べる量や食べる速度など、よく観察してあげることが変化に気がつく大事なことですので、心がけてください。

認知機能や関節のケアを考えた成分や、シニア犬にとって重要と言われる成分DHA&EPA(オメガ3脂肪酸)、犬の関節の成分となるグルコミサンやコンドロイチンなどを配合したドッグフードも増えてきました。
肥満対策として低脂質でありながら栄養価の高いドッグフードがたくさんあるので、シニア犬の食事の対策として検討してみると良いと思います。
老犬の散歩はどうすれば良い?

若い頃から散歩が好きだった犬であれば、き老犬になっても「しっかりお散歩に連れていこう」と努力される飼い主さん方が多くいらっしゃると思いますが、「老犬」のペースに合わせたお散歩内容にシフトしていきましょう。
間違えても止まったりしたときに、引っ張って急がせてはいけません。
人のように「年を取ってきたから自分なりに動きをセーブしよう、セーブしなくては!」という感情は犬には湧きにくいものです。ですから、疲れきってしまうほど歩かせても行けません。
よく眠っているところを無理矢理起こしたり雨風がすごいところを「毎日行っていたから」と無理することはありません。
天候が良く元気そうな日は長めに、よく眠っている日はそのままに、車で出掛けられるような場所や機会があれば日向ぼっこ程度でも連れていってのんびりするのも良いでしょう。
もちろん目に見えて運動がまだまだできるようであれば、急旋回させたり高く飛んだりさせないように走らせてあげましょう。
老犬もそれぞれですから、臨機応変に対応してあげましょう。
老犬の最期

老化により頻発する病気によって最期を迎えるのか、老衰で最期を迎えるのかによって全然違うと思います。
人間よりも延命に関しては愛犬家それぞれの考え方がご意見があるかと思います。
高度な医療をもってして延命措置をしていくのか、ゆっくり最期を迎えるために自宅でなるべく一緒にいてあげるのか、ペット医療が進化していく中、選択肢は広がっています。
少し悲しい話ではありますが、私の友人の話を挙げます。
友人の愛犬は癌でなくなりました。
最期の数日、酸素吸入ボックスを自宅に借りて過ごさせてあげる方法もありましたがかなりの高額だったそうです。
すでにご飯を食べる力はなく時間の問題でした。
私の友人はなるべく穏やかに同じときを過ごすことを選び、看取ることができました。
犬は家族ですが「この動物を飼っている人」として、納得できる、責任のある冷静な判断をすれば、正解不正解は無いのだと私は考えます。
老犬の飼い方・接し方|老犬介護を考えるまとめ

目や耳、食欲、足腰、、、色々と気にかけてあげないといけないことがあります。
自分だけで観察しても気づかない老化現象や病気があるかもしれません。
7歳を過ぎたら定期的に健康診断を受けたり、不安なことは獣医さんに積極的に相談していきましょう。
犬は人と違って、老いたことに対する落ち込みや抵抗はありません。
日々を過ごしていくだけです。
そんな犬たちに元気をもらえるのは飼い主さんの方かもしれませんね。

今回は、老犬の飼い方・接し方、介護について考えてみました。
冨塚ドッグトレーナーがおっしゃる様に、まずは愛犬の変化を真っ先に気づいてあげる事が大切だと感じました。犬の介護は長期化するケースもあるでしょう。
可愛い愛犬の老後の介護とは言え、時には疲れてしまいストレスに感じてしまう事もあると思いますし、分からない事も出てくると思います。そんな時は無理をせず、時にはペットシッターや老犬介護のプロに相談する事も大切だと思います。今は老犬の飼い後を専門にしたペットシッターサービスも増えて来ていますので、そういったサービスも上手に活用しながら、愛犬の老後の生活を支えてあげられたら良いなと感じました。
自分の愛犬が老後の生活をする姿はあまり想像できなかったりもしますが、長生きしてくれれば必ず訪れる事ですので、今回はちょっと切ない気持ちもありましたが『老犬の飼い方・接し方、それから介護について』向き合って考えてみました。

















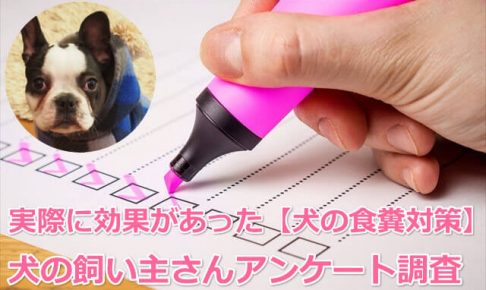












その中で特に多かったのが、「老犬の飼い方、接し方、注意点」という老犬に関するご要望でした。
早速、冨塚ドッグトレーナーに相談をし、
老犬の飼い方、接し方、介護のエピソード、老犬の食事など、老犬を飼うにあたり飼い主が不安を抱く点について共作でまとめてみました。
わが家のフレンチブルドッグうたも、まだ3歳ではありますがいずれ老犬になります。
老犬の飼い方・接し方には必ずぶち当たりますので、とても大切なテーマだと思います。