犬の糖尿病とは
哺乳類の血糖値は通常食後に増加し、膵臓ランゲルハンス島の内分泌細胞から分泌される「インスリン」によって調節されています。
しかしなんらかの原因でインスリンが分泌されない、またはインスリンの受容体(ホルモンを認識し、細胞に指令を与える構造)が機能しない場合、血糖値の調節ができなくなり糖尿病が発症します。
糖尿病という名前は尿中に糖が検出されることに由来しますが、実際尿中に糖が出てくるのは血糖値が非常に高い場合のみに限られます。
糖尿病は大きく分けて以下の二つのタイプに分けられています。
Ⅰ型糖尿病
インスリンを分泌するランゲルハンス島(膵臓)の細胞が壊され、インスリンの絶対量が不足するため発症する糖尿病
Ⅱ型糖尿病
肥満などが原因となり、インスリンの受容体が機能しないため発症する糖尿病
犬ではその半数がⅠ型糖尿病だと考えられており、その他はクッシング症候群、膵炎、高プロジェステロン血漿などに関連し発症します。そのため多くの症例でインスリン治療が必要となります。
一方人および猫ではⅡ型糖尿病が圧倒的に多く、食事・体重管理などで治療が奏功する場合もあります。
好発犬種
好発犬種は知られていませんが、8歳以上の高齢犬で多く見られる病気です。また、雄よりも雌の発症が多いとされています。
犬の糖尿病の症状
糖尿病に罹患した犬は、主に以下のような症状が認められます。
1.多飲多尿
糖が尿中に漏出することにより、腎臓は糖と共に大量の水分を尿中に出すようになります。そのため多尿が起こり、多飲に繋がります。
2.体重減少
糖尿病が発症すると、糖が血液中に高い濃度で存在するようになるため、体がエネルギー源として糖を利用することができなくなります。動物の体は糖の代わりに筋肉や脂肪をエネルギー源として利用するため、徐々に体重が減少します。
代表的な糖尿病の合併症としては白内障、糖尿病性腎症、尿路感染症、脱毛などがありますが、基礎疾患がなければ通常犬は活発で元気に見えます。合併症のうち糖尿病性腎症は不可逆的で慢性腎不全に繋がるため注意が必要です。
また、クッシング症候群や膵炎に糖尿病が併発している場合は、それらの疾患の症状が見られることもあります。
犬のクッシング症候群の詳細はこちらを参考にしてください
犬のクッシング膵炎(すいえん)の詳細はこちらを参考にしてください
犬の糖尿病の原因
犬の糖尿病の多くは、加齢に伴いランゲルハンス島細胞の変性が起こることに起因します。他にクッシング症候群や膵炎に続発するもの、雌犬に見られる高プロゲステロン血漿(発情など)に続発するものがあります。
またわずかですが、先天性糖尿病やⅡ型糖尿病に類似する糖尿病も存在します。犬では人間と異なり、Ⅰ型糖尿病が多いため遺伝性の糖尿病は多くありません。
犬の糖尿病の検査・治療
血液検査による高血糖の確認、尿検査による尿糖の確認、および臨床症状から糖尿病と診断します。基礎疾患の診断のために、エコー検査やレントゲン検査も行います。
糖尿病の治療の目的は、多飲多尿や体重減少などの臨床症状を改善し、糖尿病性腎症などの合併症を防ぐことにあります。基本的な治療は以下の3つに焦点を当てて行われます。
1.インスリン療法
犬の糖尿病はほとんどがインスリン量の絶対的不足により起こるため、通常1日2回のインスリン皮下注射が必要になります。
インスリンの皮下注射は間違えると低血糖を引き起こし命に関わるため、担当獣医師の指示に十分従って行なってください。通常インスリン療法を開始する前に、数日犬を預かりインスリン量を決定します。
2.食事管理
犬用の糖尿病処方食は食物繊維が多量に含まれており、食後の一過性高血糖を抑制するように設計されています。可能であれば療法食に切り替え、適度な運動を行いましょう。またおやつなどの間食は、高血糖を引き起こすため極力控えます。
3. 避妊手術
糖尿病と診断された未避妊雌犬は可能な限り避妊手術を行なった方が、血糖値コントロールが行いやすくなります。
犬の糖尿病は生涯に渡りインスリン注射を必要とする場合が多く、処方食やインスリン注射器の継続的な購入、定期的な血液検査による血糖値のモニタリングも必要となるため、必然的に毎月1.5万円〜程度の出費がかかります(犬種により異なります)。
また、飼い主が愛犬にインスリンを皮下注射しなくてはいけないことや、血糖値コントロールが難航し頻繁な通院や入退院を繰り返す症例もいるため、飼い主様に精神的負担がかかることもあります。そのため、担当獣医師との信頼・連携が非常に大切です。
合併症である白内障は治療を行なっていても発症してしまう場合がほとんどですが、予後は基礎疾患や血糖値コントロールの程度によって大きく変わります。
犬の糖尿病の重症化について
一般的に糖尿病の犬は活発で元気に見えます。しかし、糖尿病になんらかの基礎疾患(膵炎、クッシング症候群、腎不全、腫瘍、炎症など)があった場合、稀に糖尿病性ケトアシドーシスという重篤な病態を発症します。
糖尿病性ケトアシドーシスは高血糖に脱水と電解質異常が加わった緊急疾患であり、出来るだけ早い治療が求められます。糖尿病の症状に加え、元気消失、食欲不振、嘔吐、下痢などの症状が見られます。
この病態はほぼ必ず入院を必要とするため、糖尿病治療中でも異常に気がついた場合はすぐにかかりつけ医に行ってください。
また、犬では稀ですが糖尿病が原因で昏睡に陥る場合もあります。
犬の糖尿病に関するQ&A
Q1.低糖・低脂肪のドッグフードは糖尿病予防に効果が期待できるのでしょうか?


Q2.子犬に低糖・低脂肪ドッグフードを食べさせても大丈夫?


Q3.糖尿病予防対策を教えてください。


Q4.糖尿病を治療しないという選択肢はありますか?

Q5.インスリンの打ち方と注意点


また、注射器にインスリンを吸うときは必ず一回空打ちをしてから、インスリンを吸うようにしましょう。インスリンの投与場所は皮下であるならばどこでも構いませんが、毎日同じ場所に打っていると皮膚が硬化してしまいます。そのため何箇所かをローテーションして使用すると良いでしょう。
特に一番大切なのは、インスリン注射を打つ前に犬が食事を取っているか確かめることです。食事を取っていない状態(血糖が高くない状態)でインスリン注射を打つと、低血糖に陥ります。また、インスリン注射に失敗したと思っても2度目は打たないことが大切です(万が一最初のインスリンが取り込まれていた場合、低血糖が起きます)。
低血糖の状態では、犬の意識レベルが低下し、痙攣が起こることもあります。インスリンを使用している犬で、異常が見られた場合は早めに動物病院に連れて行きましょう。緊急用にインスリンを常用している家では、低血糖対策用に砂糖水などを用意して置くのも良いかもしれません。
犬の糖尿病|獣医師体験談とアドバイス

症例は9歳、雄のミニチュアシュナウザーで、最近一回の尿量が多いとの主訴で来院しました。とても活発・興奮しがちなシュナウザーで初診時には体重減少も認められませんでした。
しかし、血液検査および尿検査における血糖、尿糖の数値が異常に高く、エコー検査により副腎の腫大が認められたため、基礎疾患としてクッシング症候群をもつ糖尿病である可能性が非常に高いことがわかりました。
基礎疾患としてクッシング症候群、膵炎、または未避妊雌である場合、血糖値コントロールは非常に難しい場合が多く、インスリン治療中には低血糖にも注意しなくてはいけません。
予想どうりこの症例も血糖値コントロールが非常に難航し、クッシング症候群の治療薬を飲みながら頻繁な通院を繰り返し、2ヵ月後にやっと適切な血糖値を維持することができるようになりました。
症例は現在も定期的に病院に通院し、血糖値コントロールを行なっています。
基本的に血糖値は病院で血液を採取し測定しますが、家での定期的な体重測定(体重減少の有無)や尿量測定(多尿の有無)をすることで、血糖値がほぼ正常に維持されているかどうかを大まかに確かめることが可能です。適切に血糖が維持されていれば、体重は減ることがなく、尿量も増えません。
犬の糖尿病管理は飼い主の努力と獣医師との連携が必要です。担当獣医師と十分相談のうえ、治療を行うようにしてください。



















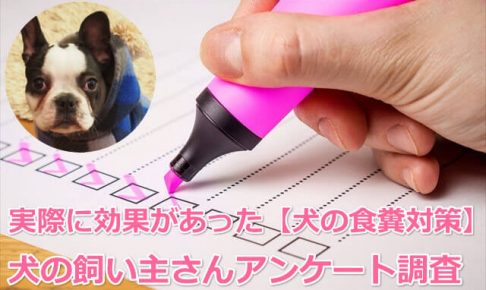












犬心 http://dog-to.com/
低糖、低脂肪のドッグフードを食べさせる事で、糖尿病の予防としてどんな点が期待できますか?