アレルギー性皮膚炎の概要と種類
アレルギー性皮膚炎とは原因となるアレルゲン(食物、ダニ、花粉など)に対し、I型(即時型)または IV型(遅延型)アレルギーを示す皮膚疾患の総称です。
犬におけるアレルギー性皮膚疾患で主要なものは以下の4つです。
・食物アレルギー性皮膚炎:食物に対するアレルギー反応を示す疾患
・アトピー性皮膚炎:環境中の物質(花粉やハウスダストなど)に対しアレルギー反応を示す疾患
・ノミアレルギー性皮膚炎:ノミの咬傷や分泌物に対しアレルギー反応を示す疾患
・接触性皮膚炎:植物などに接触することによってアレルギー反応を示す疾患
この中でも最も多いのが食物アレルギー性皮膚炎とアトピー性皮膚炎です。そこでこの項目では主に食物アレルギー性皮膚炎について説明します。アトピー性皮膚炎についての説明はこちらのページをご確認ください。
食物アレルギー性皮膚炎の原因
食物アレルギー性皮膚炎は、食物に含まれるタンパク質を体の免疫機構がアレルゲンと認識してしまうことにより、IgE抗体反応(I型アレルギー)またはリンパ球反応(IV型アレルギー)が起こることにより発症します。
犬における食物アレルゲンとして一般的に多いものは牛肉、乳製品、小麦、大豆などです。
食物アレルギー性皮膚炎の好発犬種
食物アレルギー性皮膚炎はアトピー性皮膚炎と混在している場合が多く、犬アトピー性皮膚炎単独発症は7%、食物アレルギー性皮膚炎単独発症は25%、混合型が67%と言われています。
そのため、食物アレルギー性皮膚炎の好発犬種と言える犬種はないものの、アトピー性皮膚炎の好発犬種と重複することが多いと考えられます。
食物アレルギー性皮膚炎の症状
食物アレルギー性皮膚炎の皮膚症状はアトピー性皮膚炎と非常に類似します。皮膚症状の好発部位は指の間、脇、鼠径部、肛門、口唇周囲、外耳であり、発赤と強い痒みを特徴的とします。
痒みが強いため患部を掻くことにより、2次的に脱毛も起こります。また皮膚の免疫力が低下するため、細菌や真菌の2次感染を伴う場合も多く、その場合はかさぶたや出血も見られます。
食物アレルギー性皮膚炎に特徴的なのは皮膚症状と共に見られる消化器症状です。食物アレルゲンに対する免疫反応自体は腸管で起こるため、軟便やまたは便の回数が一日3回以上と多いことがあります(必須ではありません)。
これらの症状は季節性がなく、若齢(少なくとも3歳未満)から発症します。
食物アレルギー性皮膚炎の診断
食物アレルギーの診断をするためには、まず外部寄生虫(ノミ、疥癬、アカラス、ダニ)、細菌、真菌感染を除外します。これらの病気が認められない、または細菌感染などがあっても再発する場合は基礎疾患としてアレルギー性皮膚疾患を疑うことになります。
食物アレルギー性皮膚炎の診断方法は大きく分けて二つあります。
血液検査によりアレルゲンを測定する方法
前述した通り、食物アレルギー性皮膚炎にはIgE抗体反応(I型アレルギー)およびリンパ球反応(IV型アレルギー)が関わっており、その反応の程度を血液検査で測定することができます。
IgE抗体反応を測定する「アレルゲン特異的IgE検査」およびリンパ球反応を測定する「リンパ球反応検査」の他に、「アレルギー強度検査」と言う個体がアレルギー反応を示しているか否かを測定する検査を組み合わせることが多いです。
「アレルゲン特異的IgE検査」:IgE反応はアトピー性皮膚炎でも起こるため、この検査ではI型アレルギーが関与している原因物質(ダニ、花粉、食物)などを検出することができます。
「リンパ球反応検査」:この検査では、IV型アレルギーが関与する原因食物を検出することができます。
利点
血液検査によるアレルゲン特定は、一回の採血で結果が出るため簡便です。
欠点
基本的にこの検査は非常に高価です。また、検出された原因食物(または環境中物質)が必ずしも現在アレルギー反応を起こしている物質ではない可能性があります。(言い換えれば、検出されたアレルゲン食物を除去しても症状が改善しない場合があります)
食事を試験的に変更することによりアレルゲンを特定する方法(除去食試験)
この方法では食事を完全に変更し症状の変化をみることにより、原因食物を同定すると共に食物アレルギーの診断をします。
新しく使用する食事は、今までに食べたことのないタンパク質が含まれている「新奇蛋白食」または食物がアレルゲンとして認識されないほど細かく分解された「加水分解食」を選択することが多いです。
フードメーカーから何種類か発売されていますが、自分で調理することも可能です(ただ個人的な意見ですが、自家製食はバランスを取るのが非常に難しいため進めません)。詳しくは担当の獣医師と相談することをおすすめします。
利点
食事を変更することによって症状が治れば、薬の服用などが必要なくそのまま食事を使い続けることができます。
欠点
食事を全て変更してしまうため、原因となるアレルゲンが完全に特定できない場合が多く、特定するためには何度も食事の変更をする必要が出てきます。
また基本的には2ヶ月は食事を変更し、その間おやつなどの副食は基本的に出来ないため、家族構成によっては試験自体が難しいです。
アレルギー皮膚炎の治療
アレルゲンが特定された場合はそのアレルゲンを除いた食事を利用し、除去食試験が成功した場合はその食事を使い続けることが望ましいです。
根本的な原因が除去できない場合は免疫抑制剤(ステロイド、シクロスポリン)やオクラシチニブを使用することにより痒みを抑制します。
獣医経験談
症例は4歳、雌、ミニチュア・ダックスフンド、耳と指先の痒みを主訴に来院しました。初回の来院時には耳からはマラセチア感染が、指先からは細菌感染が発見されたので抗生剤と抗真菌剤を処方し様子を見ることとしました。
しかし、薬の処方により細菌と真菌が認められなくなったのにも関わらず数週間経っても痒みが止まりません。飼い主様にもう一度お話を伺うと、どうやら小さい頃からずっと足先を舐める癖があるとのことでした。
そこでアトピー性皮膚炎または食物アレルギー性皮膚炎を疑って、検査の提案をしました。金銭的な面から飼い主様は除去食試験を選択されたため、2ヶ月間水道水と新しい食事(この時は加水分解食を使用しました)以外は一切与えないことを決め診察は終わりました。ただ、どうしても痒みが強い時のためにステロイドの内服は処方しました。
次の診察は1ヶ月後でしたが、その際はあまり効果は感じられないとのお話でした。しかしステロイドを使用して痒みを止める頻度は減ったとのことでした。
2ヶ月後の最新では指先の腫れも治り、ステロイドを使用しなくとも皮膚症状が無くなったため食物アレルギー性皮膚炎と診断しました。
この後複数回食事を変更することにより原因物質の特定も可能ですが、飼い主様はそれを望まなかったため、現在もこの子は加水分解食を食べ続けています(普通の食事なので長期間使用による欠点はありません)。
この症例のように一回で満足いく結果が得られることは少ないですが、食物アレルギー性皮膚炎は原因さえわかれば薬を使用しなくても治る病気です。そのため根気強い治療・検査が進められます。

















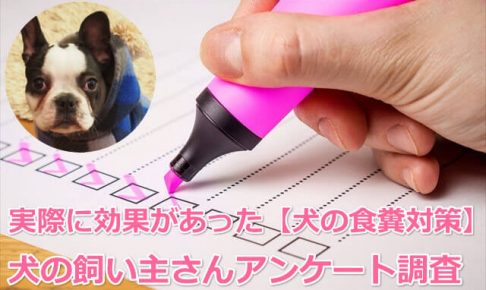












コメントを残す